|
みなさんは、ヴィヴァルディの肖像画は全部で何点現存しているとお思いになりますか?答えは、新発見の分をふくめて7点です。実は、もう一枚油絵の肖像画が発見されて、15年ほどヴィヴァルディだと思われていたのですが、後で述べるようにヴィヴァルディの身体的特徴とは相容れない決定的な違いが見つかり、まったくの別人だということが判明して、一件落着しました。
解説の内容は引用した各論文に立脚していますが、私自身が調べたことも付け加えてありますので、ご承知おきください。原文の表記ですが、いつものことながら、文字化けを起こさないように、ドイツ語の母音の上につける二つの点やフランス語のcに付けるしっぽなどの特殊文字はプレーンな文字にしてあります。また、イタリア語のアクセントはすべてアポストロフィで代用してあります。
- ピエール・レオーネ・ゲッツィPier Leone Ghezzi(1674−1755)が、オペラを引っさげてローマに乗り込んできたヴィヴァルディを描いた、1723年の記入のある肉筆戯画で、この「赤毛の司祭」サイトの扉絵で使われています。これには、ゲッツィ自身の手で「赤毛の司祭。1723年のカプラニカ劇場上演演目のオペラを作った作曲家」Il
Prete rosso Compositore di Musica che fece L'opera a Capranica
del 1723(大文字小文字はママ)というキャプションが書き込まれています。この戯画はアルベルト・カメッティAlberto
Camettiがヴァチカン教皇庁図書館のオットボーニ・コデックス(古写本)の中にあるのを発見し、パンシェルルが1930年に公けにしたものです。
(ロラン・ド・カンデ:『ヴィヴァルディ』、白水社、1970年、115ページより)
 |
- フランソワ・モレロン・ラ・カーヴFrancois Morellon La Caveが、作品8の刊行(1725年)にあたり作成した版画。これには、ラ・カーヴがラテン語で「アントニオ・ヴィヴァルディの像」Effigies
Antonii Vivaldiとキャプションを付けています。作品8にはヴィヴァルディ自身の献呈辞が付いていますので、少なくとも、このラ・カーヴの版画と上のゲッツィの戯画の2点は、ヴィヴァルディ本人も見て確認している絵です。
(Francois Frages − Michel Ducastel−Delacroix,
"Au sujet du vrai visage de Vivaldi: essai iconographique,
in VIVALDI VERO E FALSO − PROBLEMI DI ATTRIBUZIONE, a cura di
Antonio Fanna e Michael Talbot, Quaderni Vivaldiani 7, Leo S.
Olschki Edizione, Firenze, 1992. より)
 |
- ボローニャで発見された作者不詳の鉛筆画。この絵の構図はラ・カーヴのによく似ていますが、線はもっと粗く、しかし顔の各部分の割合がラ・カーヴのより自然で、また、体の向きがラ・カーヴのとは左右逆という点で、ラ・カーヴとコールドウォールの中間といった感じです。このデッサンには書入れがあり、『歌手にして作曲家のヴィヴァルディ』Vivaldi,
cantante e compositore di musicaとあります。
- ジェイムズ・コールドウォールJames Caldwall(1739−1820)によるラ・カーヴの模写。ただし、体の向きはラ・カーヴのとは左右逆になっています。これはジョン・ホーキンズ卿(1719−89)が1776年にロンドンで出版した上下二巻の大著、『音楽学と音楽実践通史』A
General History of the Science and Practice of Musicの中で用いるために作成された版画です。ところで、『ヴィヴァルディ
生涯と作品』(p.56)ではホーキンズがホーキンスに、コールドウォールがコールドウェルとなっています。前者はご愛嬌としても、後者では20世紀アメリカ文学の代表的作家の名前になってしまいます。あいにくフランス語の原書を持っていませんが、たしかに英語版ではCaldwellとなっています。早川氏は「訳者あとがき」で、このパンシェルルの著書には英訳本で始めて出会ったと書いていますから、おそらく、原書ではなく英訳本を底本に訳出したために起きた孫引き上のミスかもしれません。
- ランベールLambertによるコールドウォールの模写。ただし、体の向きはラ・カーヴのと同じ。これは、ランベールが1818年にパリで出版した『ヴァイオリンの名器と故人を含めたヴァイオリンの名工肖像画集』
Galerie des violons et luthiers celebres, morts et vivantsのために作成した版画です。この本の題名ですが、『ヴィヴァルディ
生涯と作品』(p.56)では、『ヴァイオリンの陳列室と有名なヴァイオリン製作者』という意味不明の訳語になっています。英語版はこの部分がフランス語の題名そのままで、最後のmorts
et vivantsもカットされていますので、きっと手に余ったのでしょう。また、『作曲家別名曲ライブラリー、第21巻、ヴィヴァルディ』の中の東川清一氏が執筆担当した「ヴィヴァルディの生涯と芸術」の添付写真(p.9)のひとつがこの絵ですが、そこにある「ヴィヴァルディがアムステルダムで描かせた云々」というキャプションは、まったくのでたらめです。作品8を出版したアムステルダムならラ・カーヴの版画ですし、後に紹介する論文に関わるところですが、当時、モデルとなる人物が最初から版画を彫らせるという習慣はなく、版画はもととなる油彩画を土台に彫られたそうですし、1723年のゲッツィの戯画の中のヴィヴァルディは実際の年齢(45歳)を映し出しているのに、1725年のラ・カーヴのほうはずっと若く描かれているからです。東川氏の創作か、あるいはこの写真の出処にもともと書かれていたのかわかりませんが、罪作りなことをするものです。
(Francois Frages − Michel Ducastel−Delacroix, ibid.,
p.175より)
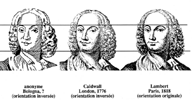 |
- ボローニャで発見された作者不詳の油絵。CDのジャケットやヴィヴァルディ関係の本で一番良く使われている絵です。発見された場所は、現在の(ボローニャ)市立音楽図書館Civico
Museo Bibliografico Musicaleの前身、ボローニャ市立音楽高等学校Liceo Musicale del
Comune di Bolognaの図書館です。余談ですが、この音楽学校の図書館の蔵書は、フランチェスコ会派の司祭でもあった音楽家ジョヴァンニ・バッティスタ・マルティーニGiovanni
Battista Martini(1706−1784)の残した膨大な楽譜を含める図書遺産がベースになっています。ロッシーニもこの音楽高等学校の卒業生です。そこの最後の図書館長だったのが、フランチェスコ・ヴァティエッリFrancesco
Vatielliで、この絵を発見したのち1938年に論文にまとめあげて発表しました。この油絵には画中の人物に関する表記が無く、そのため、いろいろと手がかりと思われるものからヴィヴァルディだ、いや別人だ、と議論を巻き起こしてきた絵です。
(Francois Frages − Michel Ducastel−Delacroix, ibid.より)
 |
- 今回、モスクワの国立プーシキン美術館で発見された、ゲッツィの手になる茶色のインクで描かれた人物画。これは、ジャンカルロ・ロスティロッラGiancarlo
Rostirollaが、背表紙に『旧世界、第一巻』Il Mondo Vecchio N.1と書かれた、ゲッツィの536枚のペン画を綴じた画集の中から発見したもので、それを音楽学者のフェデリーコ・マリーア・サルデッリFederico
Maria Sardelliが、2002年に論文にして公けにしたものです。この絵のキャプションは、これまで知られていた戯画のとは、ごくわずかに異なっていて、「赤毛の司祭。作曲家で1723年のカプラニカ劇場上演演目のオペラを作った」Il
Prete rosso Compositor di Musica e fece L'opera a Capranica del
1723となっています。
(Federico Maria Sardelli, "Un nuovo ritratto
di Antonio Vivaldi"STUDI VIVALDIANI 2, Istituto Italiano Antonio Vivaldi, Fondazione Giorgio Cini, Venezia, 2002, p.109より)
 |
肖像画をめぐる最初の論文は、1992年にイタリア・アントニオ・ヴィヴァルディ協会が"Quaderni Vivaldiani(ヴィヴァルディ研究)"の第7巻として、1992年にフィレンツェのオルシュキOlschki社から出版した『ヴィヴァルディをめぐる真贋』VIVALDI
VERO E FALSOに、フランソワ・ファルジュFrancois Fargesとミッシェル・デュカステル=ドゥラクロワMichel
Ducastel−Delacroixが共著で発表した「ヴィヴァルディの本当の顔に関して−図像学的試論」 (Au sujet
du vrai visage de Vivaldi: essai iconographique, pp.155−79.)でした。ここでは、ラ・カーヴ、ランベール、コールドウォールらの版画、ボローニャの鉛筆画、ボローニャの油彩画、そしてヴィヴァルディだと思われていたまったく別人の油彩画を、倍率や顔の向きや首の傾きなどがすべて等しくなるようコンピュータ上で処理してから、ひとつひとつゲッツィの戯画とモンタージュ写真の技法で眉、目、鼻、唇、顎の位置を比較しています。
なぜ、ゲッツィの戯画が基準に選ばれたかというと、当時の年齢がそのまま出ているだけでなく、全体として容貌上の特徴がよく伝わっている点を挙げています。それに、強調のために部分を拡大縮小しているとは言っても、全体のバランスを大きく崩すほどでなく、たとえば、大きく突き出た鷲鼻はゲッツィの戯画で一番目に付くところですが、ラ・カーヴの版画と比較してもラ・カーヴよりやや短いほどで、強烈な印象を与えるほどには長さを誇張して描いていないと指摘しています。ゲッツィの戯画から得られるヴィヴァルディの顔の特徴とは、次のようなものです。ただし、誇張した鼻は、ゲッツィのに限らず18世紀前半の戯画に広く見られる特徴だそうです。
i) 大きく突き出た鷲鼻。
ii) 後へ傾斜した額。
iii) しゃくれた顎。
iv) くぼんだ眼窩。
v) 強い弧を描く眉。
vi) 湾曲する薄い唇。
vii) 薄い体毛で痩せ型。
そして、これをまずオランダ人のラ・カーヴの版画と比較して見て、モンタージュ的にほぼ一致するが、口の形が異なっているのは、リオムも指摘している不釣合いに大きな右手が示すように、画家としてのラ・カーヴの腕があまり良くなかったせいだろうと推測しています。また、ラ・カーヴの方が2年後に刊行された絵なのに若く描かれているのは、この版画を彫るにあたってラ・カーヴが手本とした、おそらく1710年から1720年の間にパリとアムステルダムの間のどこかで描かれた肖像画が、未発見で存在している可能性を示していると述べています。
次に、ボローニャの鉛筆画と比較して、ラ・カーヴの版画と同様、モンタージュ的にほぼ一致するが、ラ・カーヴのに見られる右上にひきつったような口の歪みが少なく、右の小鼻から頬にかけて斜めに下る深い筋もかなり薄められれ、瞳の色も濃い。この鉛筆画が持つこうしたラ・カーヴの版画との差異は、そのままコールドウォールの版画に受け継がれていると指摘しています。ただし、鬘の形はラ・カーヴのとほぼ同じです。
ところで、ミラノで発見され、しばらくヴィヴァルディだと思われていた肖像画は、ヴィヴァルディ研究家コルネーダーの1978年の論文を皮切りに、4年ほどいくつかの論文で言及されますが、忽然と姿を消して20年ほど行方不明になってしまいます。それを大変な努力の結果探し当てたのが、イタリア・アントニオ・ヴィヴァルディ協会の現会長で、AGORAから『グリゼルダ』のCDを出した指揮者でもあるフランチェスコ・ファンナでした。ミラノのガッリーニGalliniコレクションにあったこの絵は個人に売却され、ミラノの南東50キロにあるピアチェンツァ近くの町にあることを突き止めたのです。実は、この絵について書かれた論文はこの絵の白黒のコピーを基にしていたので、実物が再発見されることで別人であることが確定しました。画中の人物はほとんど灰色となった黒い髪の持ち主だったのです。うっすら口ひげを蓄えた僧服の作曲家の顔は、ラ・カーヴのと比べても一体どこが似ているのかと思いますが、モンタージュ技法による顔の各部分の配置もまったく一致しません。画面手前の楽譜の記譜法が確かに1700年以前の古い様式であるのも読み取れ、年齢から言ってヴィヴァルディと同定し難かったのですが、決定的な決め手が髪の色だったのがいかにも「赤毛の司祭」らしいですね。
(Francois Frages − Michel Ducastel−Delacroix, ibid.より)
 |
ボローニャの作者不詳の油彩画を発見したヴァティエッリが、その絵をヴィヴァルディの肖像画と判断したのは、「明るい色の装飾用かつらの下からはみ出ている赤い髪」を向かって右側のこめかみのあたりに認めたからですが、これに関しては、たしかにそこには鉛を原料とする黄色と黄土色の絵の具が見られるが、同じような筆のタッチは耳や頬の部分にも見られるので、これは白く描かれた額の隆起した部分を際立たせるためのグラデーションであり、裕福さの象徴であるヴォリュームたっぷりのかつらだということを示すために付けた影に過ぎないと述べています。さらに、この絵のモンタージュ技法による顔の各部分の配置が、ゲッツィの戯画ともラ・カーヴの版画とも合わず、主に以下の点が異なると指摘しています。
i) ゲッツィやラ・カーヴのよりも目が細くて小さい。
ii) 眉と目の間が狭い。
iii) 額は後へ傾斜してなく、額の骨が浮き出て垂直に切り立った感じ(向かって右側のこめかみのあたりにそれを示す濃い影)。
iv) こうした特徴は、むしろベネデット・マルチェッロを描いた版画に共通するので、この肖像画はヴィヴァルディではなく、ベネデット・マルチェッロなのではないかという議論もあったそうです。特に、目と額の感じが驚くほど似ているそうです。しかし、それに反論したのが「赤い地毛」論者でもあるトールバットでした。画中の人物を描く道具立てとして、楽譜と共にヴァイオリンを描き込んでいる以上、ただの素人の音楽愛好家ではなく、プロのヴァイオリニスト兼作曲家であることを表している、したがって近辺に該当する音楽家を求めればやはりヴィヴァルディということになる、と判断したそうです。
というわけで、この人物をヴィヴァルディであると認めるには、大前提である「地毛の赤い髪」など描かれていないこと、モンタージュによる顔の造作の不一致、目の形、目と眉の距離それに額の形が、ラ・カーヴ、ゲッツィ、ボローニャの鉛筆画では互いによく似ているのに、このボローニャの油彩画だけ一致しないという点で、この人物をヴィヴァルディと断定することに大きな疑問を表明しています。のちにトールバットはMASTER
MUSICIANS: VIVALDIの改訂増補版の注の中でこの論文に付いて触れて、ヴァティエッリも自分もこの絵がヴィヴァルディだと信じているが、最新のもっとも詳しい研究はそれに疑問を呈していると述べています(p.169.)。
この論文にまっこうから噛み付いたのが、INFORMAZIONI E STUDI VIVALDIANIの第15巻pp.99−113.(1994年)に掲載された、「赤い前髪およびその他の詳細。ヴィヴァルディの図像の再考のために」Ciuffi
rossi ed altri dettagli. Per una riconsiderazione dell'iconogafia
vivaldianaという題の論文です。著者は新発見の肖像画について論文を発表したフェデリーコ・マリーア・サルデッリですが、彼はこのファルジュとデュカステル=ドゥラクロワが採ったモンタージュ技法について、コールドウォールやランベールの手によるまったく当てにならない肖像画も対象にしているだけでなく、手法やスタイル、技術、腕前がそれぞれ異なる画家の作品を等しく同レベルで扱うなど、無意味かつ根源的に不可能であると、手厳しく批判しています。その上で、ヴァティエッリ以来トールバットに至るまで、ボローニャの油彩画がヴィヴァルディであると断定する根拠となった「赤い地毛」については、17世紀から18世紀にかけて、少なくともヴェネト地方では、キャンバスの下塗りに焦げ茶から黄土色の間の暖色系が使われ、とりわけさまざまな色調の赤みがかった橙色が主流を占めていたと述べ、装飾用の白いかつらの下からはみ出て見える赤毛とは、他ならぬこの下塗りの絵の具の色である、と断じています。画家がそこに下塗りの色を生かした理由として、かつらと額の境目をかつらに量感を持たせてぼんやりと分けるためで、さもないと白いコザック帽をきちっとかぶったような印象を与えてしまうからだ、と推測しています。
ところで、サルデッリはここで面白いことを指摘しています。フランソワ・ファルジュとミッシェル・デュカステル=ドゥラクロワ共著の論文の内容とは異なることになるのですが、赤い髪がはみ出ている部分は、ヴァティエッリではかつらの真ん中の分け目あたりだったのが、コルネーダーの頃から左のこめかみあたりということになったそうです。この左のこめかみあたりにはみ出ている赤毛というのは、サルデッリもファルジュとデュカステル=ドゥラクロワに同意見で、額の骨の隆起している部分を際立たせるために赤味がかった茶色で作った陰影だと述べています。
さらに、肖像画の道具立てについては、この論文の直前に掲載されている「アントニオ・ヴィヴァルディのポートレート」Ein Portrat
Don Antonio Vivaldis(pp.83−98)の著者、ユッタ・ヴェンデJutta Wendeのように、指輪やインクつぼの中のペン、作曲中と思われる手前の楽譜が五線譜ではなく四線譜であることなどに、人物を特定するヒントが隠されていると見る見解に対して、この絵の作者は顔の描写に神経を集中しすぎて疲れてしまい、画中の人物がヴァイオリニストにして作曲家であるということを伝えるだけで精一杯で、道具立ての描写については気が抜けてしまった。そのため判読不明な四線譜や、手にしているヴァイオリンの遠近法的間違いなどのミスを犯したのだろう。道具立てに謎解きを求めるなど無意味なことで、指輪を指にはめているのは実際に指輪をはめていたからで、インクつぼに二本目のペンが立ててあるのは、ヴィヴァルディはペンを二本持っていたからで、それにペンが立ててないとジャムの容器にも見えるからだと、皮肉まじりにばっさり切り捨てています。
では、サルデッリもこの絵をヴィヴァルディ以外の人物であると見ているかというと、それがまったく逆で、同定の決め手として「かつらの下からはみ出た赤い地毛」というのは、ヴィヴァルディが赤毛だったという事実を知った上で絵を見たために起きた錯覚で、そのようなものは存在しないが、
i) 隆起した額はゲッツィの絵のとおり後ろに傾斜している。
ii) ラ・カーヴの版画より目が細いのは、ラ・カーヴがその版画に描いた右手と同様に誇張しすぎた結果で、そんなに大きくない。コールドウォールでは普通のサイズに戻してある。
iii) 少し上唇が飛び出たハート型の唇、装飾用かつらの収まり具合、二重あご、楕円形の額、瓜実顔がラ・カーヴの版画とよく似ている。
との理由から、ヴィヴァルディだと断定しています。
さて最後に、最近モスクワで発見されたゲッツィによるペン画ですが、この肖像画はINFORMAZIONI E STUDI
VIVALDIANIの後身であるSTUDI VIVALDIANIの第2巻pp.107−14.(2002年度)に、フェデリーコ・マリーア・サルデッリが「アントニオ・ヴィヴァルディの新たな肖像画」Un
nuovo ritratto di Antonio Vivaldiと題して発表した論文で初めて世に知られるようになった作品です。今まで知られていた戯画は206mm×280mmの紙に描かれたものですが、今回見つかった絵のほうは、94mm×66mmと、かなり小さな紙です。ただ、前作は同じ紙に高位聖職者があと二人描かれていますが、今回のはヴィヴァルディだけで、線の数はもっと多く、タッチもずっと精緻で戯画的な要素が薄まっています。それと、キャプションがほんのわずか異なっていて、前作では「赤毛の司祭。1723年のカプラニカ劇場上演のオペラを作った作曲家」Il
Prete rosso Compositore di Musica che fece L'opera a Capranica
del 1723でしたが、こちらは「赤毛の司祭。作曲家で1723年のカプラニカ劇場上演のオペラを作った」Il Prete
rosso compositore di Musica e fece L'opera a' Capranica del 1723と、関係詞cheではなく接続詞eで結ばれています。それに、筆跡も走り書きではなく、落ち着いて書いたようでもっと丁寧な字体です。
なぜ、よく似た構図の絵が存在しているかというと、ゲッツィにはまずさっと胸像画の形で人物の特徴をスケッチしておき、時間がたってからゆっくり落ち着いて天賦の才能ともいえる驚異的な記憶力をもとに、改めてスケッチに肉付けを行っていき、やがて全身の肖像画を完成していくという習慣があったそうです。そうすることでモデルに二重に手間を取らせないで済んだからです。ことにヴィヴァルディの場合は、前作の戯画的スケッチの構図から見て、ほかの二人と一緒にいるところを間近に観察し、しかもヴィヴァルディの性格をよく知った上で描いているので肉付けには信憑性がある、というのがサルデッリの論旨です。
新発見の肖像画の元となった戯画風スケッチに、ヴィヴァルディと向き合う格好で描かれている二人は誰なのか、またどこで描かれたのかという点について、サルデッリは以下のように述べています。若い方はカゾーニCasoni枢機卿の「血のつながった甥」"nepote
carnale"で、老人はマッフェオ・ファルセッティMaffeo Farsetti卿です。このファルセッティという人物は、ヴェネツィアの高位聖職者で、のちにローマ教皇ベネディクトゥス(またはベネデット)13世によりラヴェンナの司教に昇進させられています。おそらくヴィヴァルディを取り巻くファンの一人で、ヴェネツィアからローマへ同行して、オペラを観劇しただけでなく、ヴィヴァルディに付き添ってローマの社交界にもデビューしたのだろう、と推論しています。ちなみに、ファルセッティのこの戯画風スケッチに肉付けした肖像画も、今回の新発見であわせて発見されています。ヴィヴァルディを含めた三人を描いた場所については、チェロとチェンバロのアマチュア演奏家でもあったゲッツィが、ジューリア通りVia
Giuliaに面した豪邸に、アカデミックなサークルを開いていたので、そこに招かれた客の中にいたこの三人を描いた可能性もありますが、非常に急いでスケッチをとり、走り書きでキャプションを入れてあることから、そうしたゆったり落ち着いた雰囲気の中ではなく、キャプションにあるカプラニカ劇場の楽屋か、あるいは貴族のサロンに招かれた際に描きとめたのではないかと述べています。
ところで、このモスクワで発見された画集には、ヴィヴァルディと関係の深いもう一人の人物の肖像画もあわせて発見されました。当時、ファルファッリーノFarfallino(小さな蝶)と
呼ばれていたジャチント・フォンターナGiacinto Fontanaです。1月20日の日付入りのキャプションには、「ペルージャ出身のファルファッリーノ。すばらしいソプラノ歌手でアリベール劇場にて赤毛の司祭のオペラに出演」Farfallino
Perugiano bravo soprano / recito' nel Teatro Alibert l'opera
/del prete rossoとあります。サルデッリによれば、アリベール劇場とはカプラニカ劇場の誤りで、ローマに乗り込んできたヴィヴァルディが最初(1723年2月)にかけたオペラ、『テルモドーン川のヘラクレス』Ercole
su'l Termodonteではイッポリート役を演じたばかりでなく、翌1724年、同じくローマのカプラニカ劇場にかけた『ジュスティーノ』ではアリアンナの役を演じています。
さて、本題に戻って、ヴィヴァルディは司祭でありながら、しかもカトリックの大本山であるローマにあってさえ、僧服の白いカラーではなく、ブルジョアの服装である胸飾りをつけ、上着の前を開けて社交界に出入りしていたことがこの絵で明らかになったのです。この点について、そこにはいかにもヴィヴァルディらしい屈託のなさが窺え、「ヴィヴァルディは一生僧服を脱ぐことがなかった」とあちこちに書かれているが、それは大きな誤解に過ぎなかったことが判明したと述べています。
以上ですが、私にはあのボローニャの肖像画と今回発見された肖像画の距離は、唇の形をのぞいて一層遠くなったような気がします。若い頃細かった目が中年以降大きな目になるとか、目と眉の間は年をとるほど近づくことはあっても離れるということはありませんし、それに、額はゲッツィでは後ろにそっていますが、ボローニャの油彩画のほうは、左右に骨が浮き出るほど垂直に切り立っているように私には見えます。じゃあ、誰なのさ?と言われても、ちょっと困りますが……。
|
